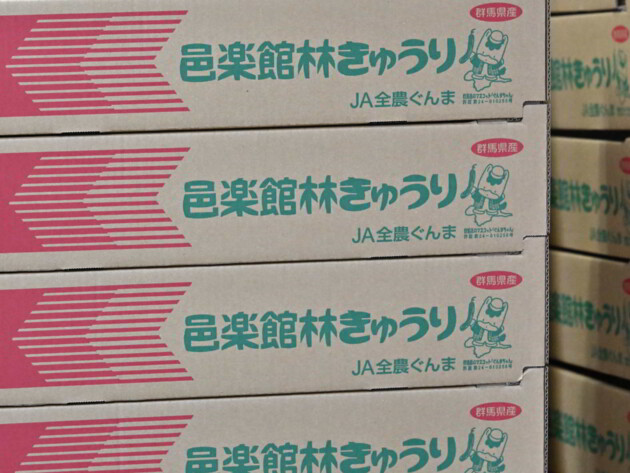大地のおくりもの
キュウリ
- 群馬県 JA邑楽館林(群馬県館林市)
- 2025年6月

水に恵まれた肥沃な土壌で育つ
キュウリ
「感覚がたいせつ」と教わった栽培でした。多忙だった日々もありました。
今では、環境制御装置の登場で様変わりしてきたようです。
東日本一の生産量を誇る、群馬県のキュウリ。なかでも夏には気温が四〇度近くになり、全国有数の〝暑いまち〟として知られる館林市と周辺の邑楽郡が、主要産地になっている。
関東平野のほぼ真ん中に位置。利根川と渡良瀬川に挟まれた地域で、キュウリ栽培が始まったのは昭和二十年代後半。JA邑楽館林青年部部長であり、キュウリ生産者の秋山晃司さん(41)は、水に恵まれた肥沃な土壌が、産地になる背景にあったと話す。
「キュウリ栽培で、たいせつな要素の一つが〝水〟です。この辺りは沼が多く、地下水もふんだんに利用できることが、キュウリ栽培にうってつけでした。豊富な日射量も地の利になりました」

補助金制度で環境制御装置を導入
肌寒さが残る春、秋山さんのハウスに入ると、頭上に張られた〝ポリカーテン〟からポタリ、ポタリと水が滴り落ちていた。室温二八度、湿度七五パーセント。温度、湿度、炭酸ガスといった栽培の環境データを、つねに最適の状態になるようコントロールしている。この日は曇天で寒かったため、保温のために頭上のポリカーテンを閉じていたが、天気がいい日は開放して、日光を当てる。
また、夜間は湿度を極力低くし、乾燥ぎみにすることで病気を予防。植えつけ直後はポリカーテンを二重にして、幼い苗に当たる日ざしを和らげるなど、時間帯や生育段階に応じ、きめ細かい管理をしなくてはならない。

秋山さんは、就農十八年め。東京農業大学短期大学部で野菜を専攻し、種苗会社で一年間の栽培研修を積んだのち、実家に戻って父が営むキュウリ栽培を継ぐ決意をした。しかし、当初は戸惑うことが多かったと振り返る。
「父からは『感覚がたいせつだ』と教わりました。キュウリの栽培環境は、『汗ばむくらいの蒸し暑さがいい』と。でも、自分の体感では温度・湿度がよくわからなかったんです(笑)。そこで、とにかく測定することが必要だと考え、八年前からは補助金制度を活用し、環境制御装置を導入しました」
キュウリは開花から収穫まで、わずか七~十日ほど。適期を逃さず、収穫して出荷しなければならない。そのため生産者は毎日忙しく、遅くまで作業をするなど、家族と共に夕食をとれないこともあったという。しかし、自動化を導入したことで、夕方六時には自宅に戻れるようになったと、うれしそうに話す。
「どこにいても、環境データを確認できるんです」
見せてくれたのは、スマートフォン。温度、湿度、炭酸ガスといった環境データを、離れていても二十四時間いつでも監視できるようになった。適正温度を設定しておけば、天窓・カーテンは自動開閉する。遠隔操作もできるため、ハウスの室温が上がりすぎてしまうといったリスクを最小限にできる。
「以前、真冬の夜中にブレーカーが落ちて暖房が止まってしまったときにも、すぐにわかりました。この装置を導入していなかったら、きっと朝まで気づかず、たいへんなことになっていたでしょうね」

環境制御装置を導入した当初、秋山さんら若手のキュウリ生産者は、勉強会をスタート。やがてメンバーは五人、十人と増え、平成三十年には「環境制御をしていること」を入会条件にし、他県のキュウリ生産者も自由に参加できるスタディクラブ「節なり会」を結成した。
現在は、管内の二十~三十代の生産者を中心に百人ほどが所属。勉強会や現地研修会を、月二回開催している。

生産者仲間を増やしたい
ところで圃場のキュウリは、すべての実がちょうど腰の高さについている。これは「ストレートつる下ろし」という栽培法によるもの。まずは主枝を十二節で摘芯し、側枝四本を上へと伸ばす。側枝の摘芯はせず、一定の高さまでつるが伸びたら、少し下ろして左隣の誘引ひもに移す。
これを繰り返すことで着果位置がそろうため、実を見逃すことがなく、収穫しやすくなる。摘芯をしなくていいため、整枝で失敗することがなく、慣れていないパート従業員でも作業がしやすい。
「多くの人に農業って楽しいと思ってもらい、生産者仲間を増やしたいと考えています。そのためにはしっかり収益になり、休みもとれる農業であることがだいじです」
キュウリ栽培のおもしろさは、どんどん実るためお金になるのも早いこと、と秋山さん。若手生産者たちがスマートで、楽しい農業の新時代を切り開き始めている。

文=加藤恭子 写真=石塚修平(家の光写真部)