JAリーダーインタビュー
徳島県JA徳島市 代表理事組合長 松田清見さん
- 徳島県 JA徳島市
- 2025年3月

誠を尽くせ 相互理解はそこから始まる
かつて農協の営農指導員として、こつこつ組織づくりに励んだ。いま、リーダーとして、多くの難問を前に、みんなの知恵をこつこつ集めている。
数億円の買い付けに「責任とれるのか」の声
─生家のある地域をご案内いただきました。豊かな水と緑に恵まれた地域ですね。
徳島市のシンボルとして知られる眉山の北西にある国府町という所です。
小学校は自宅から歩いて一分。よく教科書を忘れたりして、休み時間に取りに帰っていました。なぜ忘れ物をするかというと、遊ぶことしか考えていなかったからでしょうね(笑)。近くに、幅一・五メートルくらいのきれいな小川が流れていて、そこでよく魚をとりました。低学年のうちは、小川を飛び越えようとして水の中に落ちたり、靴をぬらしたりしましたが、運動神経はよかったみたいでね。今もゴルフを趣味としていますが、小さい頃からの健脚が生かされているのかもしれません。
父は専業農家で、農地は田んぼの他に畑が十アールくらい。トマトやキャベツ、ホウレンソウなどを作っていた記憶があります。冬場は、学校から帰るとトンネルハウスの上に保温用の菰をかぶせていました。早く遊びに行きたいから、友達にも手伝ってもらっていました。
自分が長男として家を継ぐという意識はありましたが、親の苦労も見てきたので、農業の厳しさも実感していました。一農家として生きるのか、行政や農協などの組織で働き地域農業を振興する役割を担うのか。いろいろな選択肢がありましたが、縁あって地元の徳島市農協に入組しました。
─農協ではどのような仕事をしましたか。
最初に花卉の営農指導員になりました。仕事は楽しかったです。とにかく、人に恵まれましたね。上司や先輩役職員から指導を仰ぎながら、日々の仕事にやりがいを感じていました。
当時、徳島県はテッポウユリの産地でしたが、球根代の高騰などで生産量が減り、価格も低迷していました。小ギクを栽培する農家もいましたが、ほとんどが地元の市場に個人で出荷していたのです。目下の命題は組織づくりでした。生産者をまとめて京阪神の主要市場に出荷することをめざし、花卉部会を発足。まずはハウス栽培のフリージアと露地栽培のグラジオラスを軸に産地振興をめざし、個人出荷の農家に、いっしょにやりませんかと声をかけました。手数料や運賃などのコストを考えて躊躇する農家には、部会長と共に訪ねていきました。みんなでまとまった量を出荷できれば経営が安定し、さらに規模を広げていろいろな花に挑戦できる、と説得したのです。
─産地づくりに一から関わったわけですね。その後、どうなりましたか。
地道に仲間を増やしていった結果、フリージアとグラジオラスは一時、全国で五本の指に入るほどの産地になりました。当然、動くお金も大きくなります。球根の買い付け額は毎回数億円にのぼるので、「責任をとれるのか」という声が内部から上がったほどです。でもわたしは楽観的でしたね。景気は上向きだったし、「国際花と緑の博覧会」(平成二年)の開催が決まったことも追い風となっていました。
そうしたなか、ユリ科のカサブランカ、シンビジウムやコチョウランといった洋ランの生産拡大もめざしました。農産物というのは十年くらいでピークが終わってしまうからです。かならずいつかは別の産地が台頭したり、消費者の嗜好や流行が変わる。今のままでだいじょうぶ、と考えていたら取り残されるでしょう。長いスパンで考え、部会員がもうかる方法を一生懸命考えることが自分の仕事だと思っていました。
その部会に仲間入りしたのは、三十五歳のときです。父が他界し、家業を継ぐために農協を退職し、花農家として就農しました。農協で培った技術や知識はもちろん、生産者や市場関係者などとの交流から学んだことが営農に役立ったと思います。

掃除によって人が見えてくる
─平成十年からJAの非常勤理事を務め、二十八年に組合長に選出されました。いまどのような課題に取り組んでいますか。
二十八年度から三年間取り組んだ営農経済事業改革では、営農経済センターの集約や組織の統廃合を進め、販売手数料も変更するなど、組合員にも多大なご協力をお願いしました。短期的には改革は農家にとっていいことばかりではないのです。ですから、その負担の見返りになりうる支援をする必要があります。できるだけ安定的な収益を上げることができる販売価格を維持するよう、共同出荷・共同販売のさらなる充実を図っているところです。
そして、農業の持続可能性と発展、食料安全保障の実現のためには再生産可能な価格設定が求められており、それには、わかりやすい情報発信と消費者の理解が必要となるでしょう。実効性のある政策が打ち出されることを期待しています。
─職員には、日ごろどんな言葉をかけていますか。
「みずから考え、みずから行動する」。それをいつも言っています。食料安全保障もそうですが、いま、わたしたちが直面しているのは、リーダー一人の考えだけで解決できるような問題ではないんです。だからこそ、トップダウンではなく、みんなが知恵を出し合って問題を解決していくボトムアップでいこうと。その知恵やアイデアを受け止め、実現するのがわたしの使命です。
管理職のみなさんは、職員一人一人が自分の考えや気づいたことを率直に言えるよう、耳を傾けてほしいですね。「自分一人の力ではなにも変えられない」と思わせない環境づくりがだいじです。
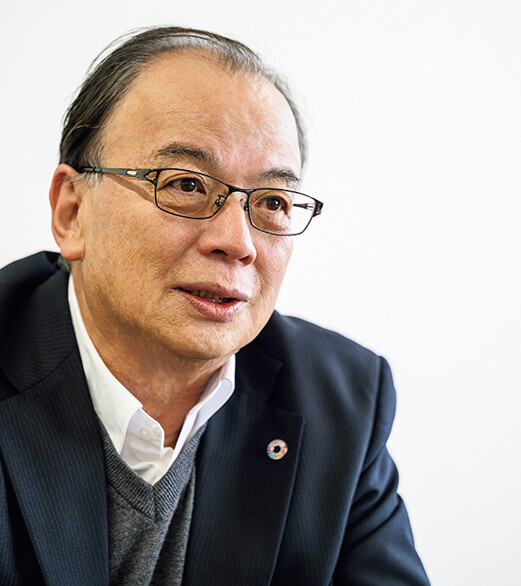
わたしは職場を明るく風通しのよいものにするため、自分たちでトイレ掃除をすることを提案しました。毎日当番を決めて名前も掲示するようにしたのです。すると、すっかりきれいになりました。みんなで使う場所に全員が責任をもって関わることで、おたがいが見え、協同活動のたいせつさを理解することができる。こうした小さな取り組みも、どんな仕事にも通じる基本であると考えています。
わたし自身も、組合長として組合員や利用者のニーズに応え、その価値を提供していくために、不断の自己改革を実践するとともに、現在のJAに求められている高度なガバナンスや内部統制・コンプライアンス態勢を構築し、これまで以上に安心してご利用いただける業務運営やJAを支える人づくり、働きやすい職場づくりを進めたいと思っています。
「誠を尽くせ」という言葉がわたしの信念です。自分の考えをしっかりと持ち、正直に生きようとする「心の誠」があれば、人は相手にたいしてなにができるか謙虚な気持ちで考えることができると思います。組合員にたいしても、役職員同士でも、おたがいを理解しながら仕事をする。そんな組織でありたいと願っています。

写真=松尾 純
 詳細情報
詳細情報
まつだ・きよみ/昭和二十八年、徳島市生まれ。徳島県農業大学校を卒業後、四十八年徳島市農協に入組。六十三年に就農し、花卉生産を開始。平成二十二年JA徳島市代表理事専務、二十八年代表理事組合長に就任し、現在に至る。令和六年JA徳島中央会代表理事会長に就任。
JA徳島市
昭和四十四年、十四総合農協と四専門農協が合併して誕生。徳島県東部に位置し、四国一の大河、吉野川など大小無数の河川が流れる水資源が豊かな土地。温暖な気候を生かして、さまざまな農産物が生産されていて、ブロッコリー、シイタケ、サツマイモ(なると金時)などの生産が盛ん。













